2020-10-15 はてなブログ タグ追加 2017-06-11 新規
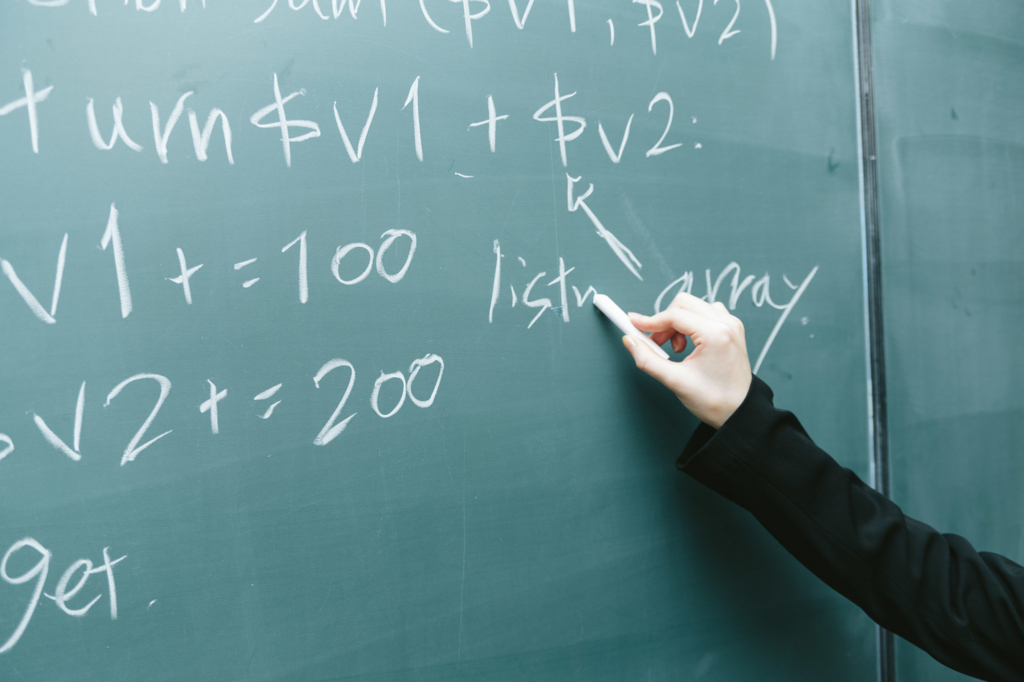
副業を考える前に時間がないサラリーマンが少しでも所得を増やすには?
目次
・"収入"と"所得"を理解すれば所得(手取り)は増える
・所得を増やすシンプルな方程式
・時間がないサラリーマンが少しでも所得を増やすには?
・給与明細の見方
・・課税、非課税項目
・・社会保険料の項目、税金の項目
・・・医療費控除
・・給与明細をざっくり図解
・セルフメディケーションやふるさと納税知ってますか?
・・セルフメディケーション
・・ふるさと納税
・医療費が掛かりすぎたら"高額療養費制度"を活用
・・これから重要"高額介護サービス費制度"
・年末調整や確定申告で清算
◆出典、転記、参考、引用◆
◇その他、著作権の定められた条件(範囲)での利用◇
ファイナンシャル・プランニング技能士3級の知識
自営業の知識
セルフメディケーション税制
知ってトクする セルフメディケーション税制
国税庁ホームページ
"収入"と"所得"を理解すれば所得(手取り)は増える

収入と所得の違いを貴方はわかりますか。
どちらも手に入れるもので間違いないのですが、定義は大きく異なります。
まず収入ですが、純粋に手に入れたものとなります。
1000円を手に入れれば1000円が収入となります。
次に所得ですが、収入から経費を抜いたものとなります。
1000円を手に入れるために何をしたかが重要です。
例えば、交通費として100円を使った場合、100円が経費となります。
1000円から100円を引いて、900円が所得となります。
原則として、この所得に税金が掛かります。
サラリーマンで言うならば、額面収入が収入となり、手取りが所得となります。
自営業で言うならば、売上が収入となり、利益が所得となります。
フリーランスの方は源泉徴収させている場合があるので、サラリーマンと自営業のごちゃ混ぜだったりします。
所得(手取り)を増やすシンプルな方程式
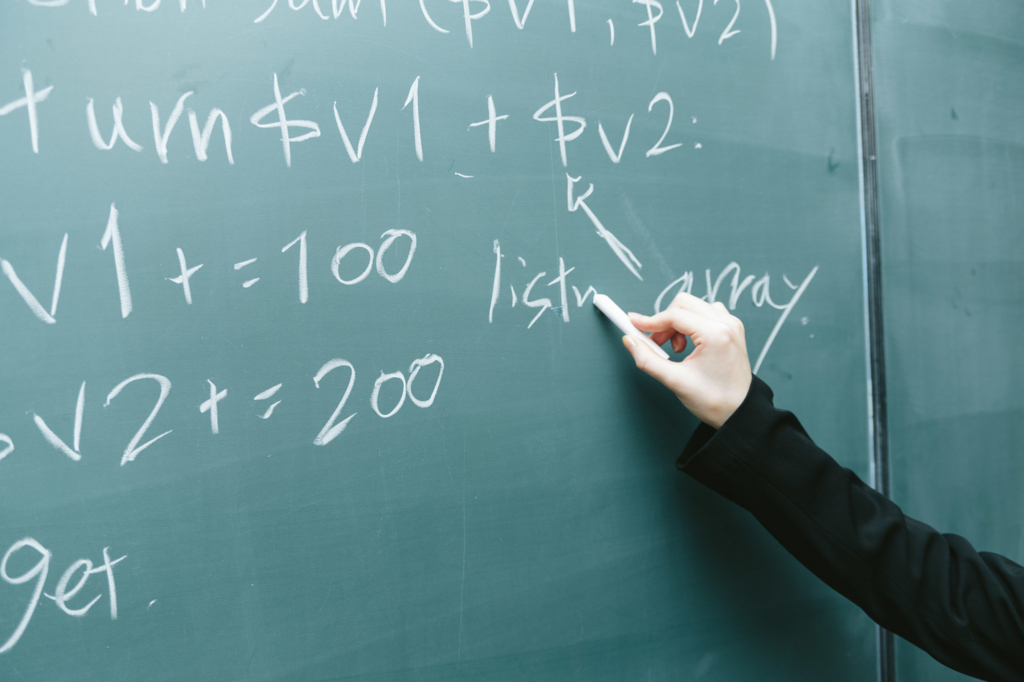
この世知辛い世の中、先立つものはお金。
少しでも所得を増やしたいものです。
実は、考え方としてはとてもシンプルです。
このシンプルな方程式を頭に入れておかないと、「いくら働いても何で手取りが増えないんだ」とか、「どんだけ働ければ楽になるのか」ということになります。
その方程式はとは・・・
👉ポイント 【収入】―【支出】=【所得】
※ここでいう所得とは、得たもので、自由に使えるものと解釈。税法上の所得とは少し違います。
所得を増やすには、方程式を見れば当たり前ですが下記のどれか。
収入を増やす
支出を減らす
どちらかしかないのです。
時間がないサラリーマンが少しでも所得を増やすには?

世間では副業を推奨しているようですが、そこは立ち止まって考えて下さい。
生活に余裕がなく、副業を通して収入を増やしたい気持ちは筆者も重々承知していますが、まず、副業する時間があるかと整理して見て下さい。
時間的に厳しい方や体力に問題ある方、他に時間を使いたい方は最初は副業するのでなく、現状を整理し支出を見直すことを筆者は推奨します。
見直すことで得られる所得もあるということです。
そのカギは給与明細が握ってます。
給与明細の見方
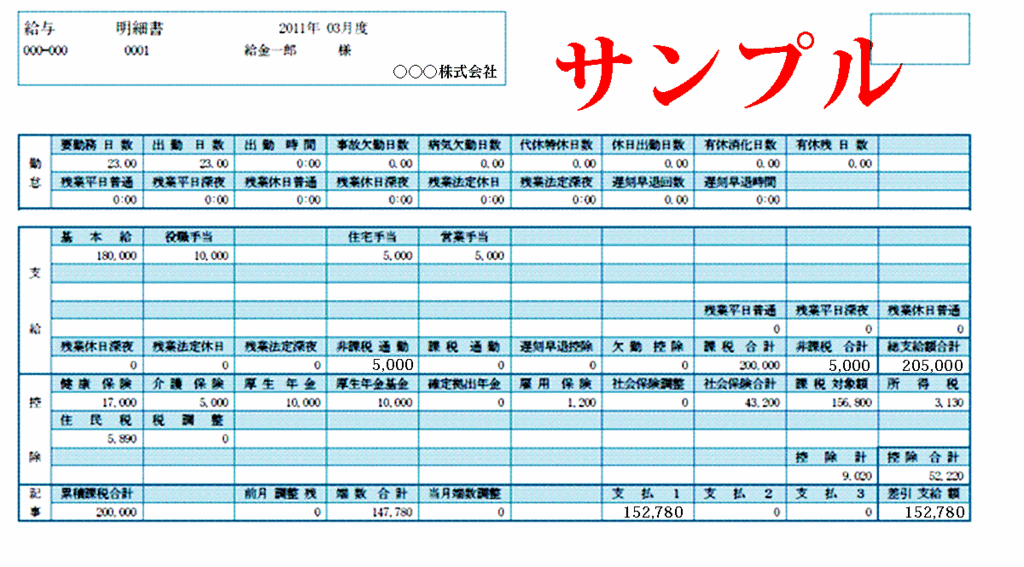
サラリーマンの方はこの給与明細が重要です。
ざっくりでいいので中身の項目を理解する必要があります。
大まかには勤怠、支給、控除、他となっていると思います。
支給から控除を引くと差引支給となり、手取りとなって口座に振り込まれるのが一般的です。
ここからが重要です。
課税、非課税項目
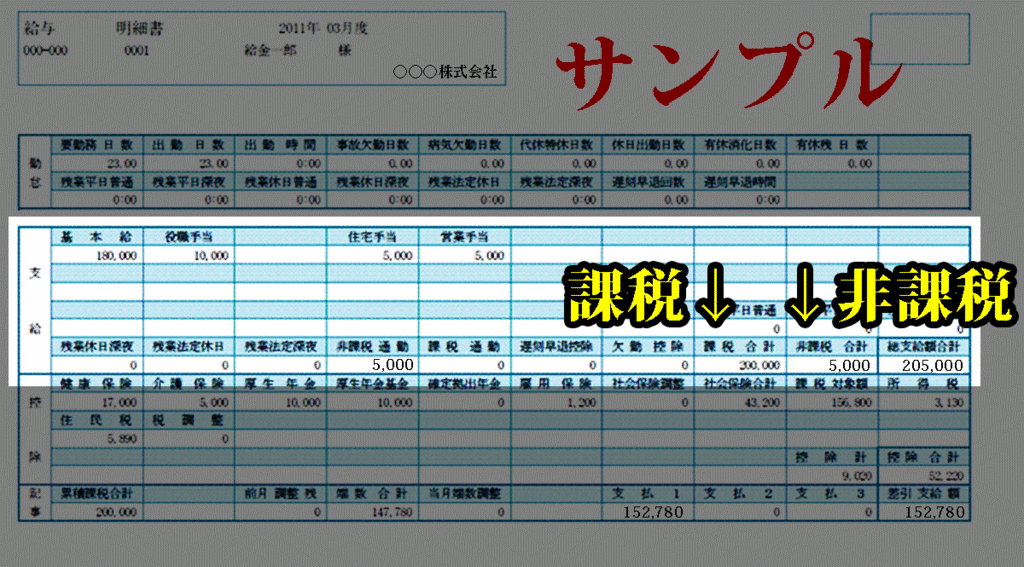
支給欄に存在する"課税合計"と"非課税合計"。
つい、総支給額合計を見がちですが、実はこの二つの項目の方が重要です。
原則、所得に税金が課されます。
つまりは、課税合計の中に税金が課せれることとなります。
課税合計から非課税合計に振替れるものがあれば、経理の人や人事の人に連絡し、相談して振替えてもらいましょう。
わかりやすい項目として、非課税交通費つまり通勤費が挙げられます。
ある程度の規模の会社であればしっかり分けられていると思いますが、規模が小さかったり、派遣の人の場合はすべて課税合計で処理されている場合があります。
その他、経費にあたる部分も非課税合計で処理できます。
経費の一部としてスーツ代なども認められる場合があります
所得を元に、所得税や住民税、保険料が計算されますので、通勤費等で所得が肥大していないかチェックする必要があります。
社会保険料の項目、税金の項目
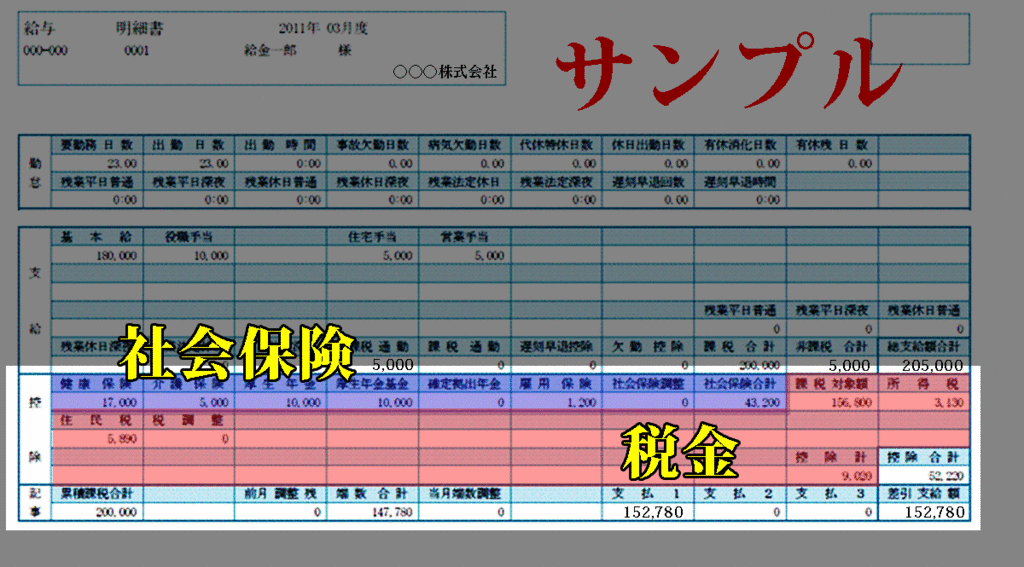
課税合計から社会保険料が引かれ課税対象額が判明します。
課税対象額を元に税金が課されます。
後で紹介するセルフメディケーション税制や医療費控除なども、課税合計(所得額)から引けます。
煩雑さも含め、通常は確定申告で計算します。
課税合計から課税対象額になる部分の処理が、一般的に言う"所得控除"と呼ばれます。
所得を数字上で抑える所得控除には、他にも住宅ローン控除を始めとする様々なものがあります。
医療費控除
日々の医療費で100,000円を超えた部分について、一定額(一部分)を所得控除できます。
予防のための費用は計上できず、あくまでも治療のためものに限ります。
給与明細をざっくり図解
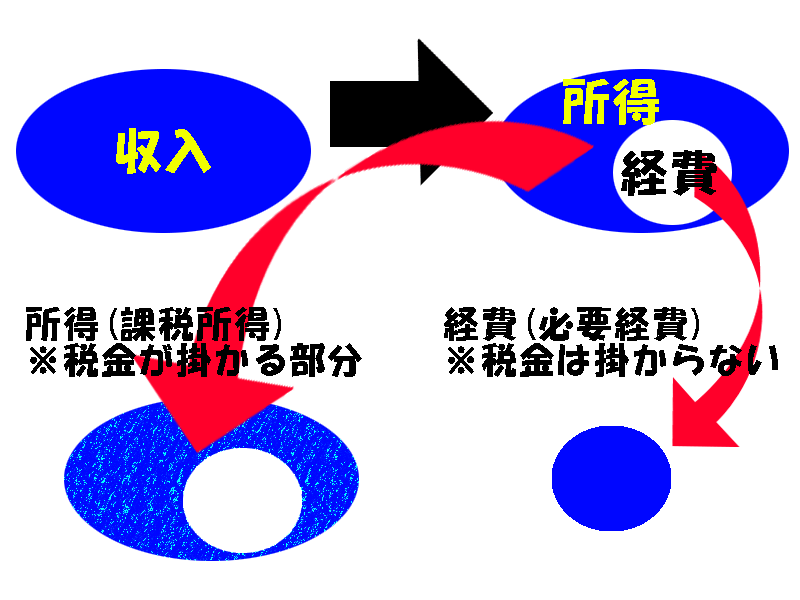
セルフメディケーション税制やふるさと納税知ってますか?

節税のために、日々の情報収集は必須です。
最近では『セルフメディケーション税制』や『ふるさと納税』が注目を集めています。
セルフメディケーション税制

医療費控除には弱点があります。
まず、1年で100,000円以上を医療費で使わなければ無縁だということ。
そして、予防医療には使えないことです。
前者を改善したのが、セルフメディケーション税制となります。
対象となるのは?
具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、
以下の定期健康診断などを受けている人が、2017年1月1日以降に、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、
医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間12,000円を超えて購入した際に、12,000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8千円)について所得控除を受けることができます。
この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり、医療費控除の一部であるため、
「従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することができない」点に注意しましょう。
従来どおり10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは、申告者自らがどちらかを選択することになります。
対象となる人は?
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかを受けている人(勤務先での定期健康診断なども含まれる)。
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査
- がん検診
対象となる医薬品は?

このマークが目印。
領収証やレシートは必ず保管して置きましょう。
👉ポイント 領収証と領収書は微妙に違います。請求書や明細書、納品書を用いて領収書の代わりとする場合があります。つまりは領収書の一つとして領収証があります。
ふるさと納税

好きな市町村自治体に納税できるというこの制度。
市町村自治体から返礼品が貰えます。
返礼品もある意味での所得です。
具体的な流れは以下の通り。
手続きは役場で確認して下さい。
- 自治体の選定
- 選んだ自治体に納税
- 返礼品貰う
- 確定申告時に納税した額から2,000円を引いた額が住民税や所得税から差し引かれる ※2,000円は手数料みたいなものです。
医療費が掛かりすぎたら"高額療養費制度"を活用

"高額療養費制度"知っていますか?
所得を著しく毀損する項目。
ズバリ!医療費です。
医療費は自動車の車検と似ているところがあり、お金を掛ければ掛けるだけ、手元から所得がなくなります。
そこで覚えておきたいのが高額療養費制度。
詳しくはお調べ願いますが、ざっくりとした内容で、1回の治療に置いて約100,000円を超えた医療費は後で全額還付されます。
※厳密には前年の所得で上限が変わります。
これから重要"高額介護サービス費制度"
高額療養費制度と似た考えで、高額介護サービス費制度があります。
同月での介護サービス費の上限設定となります。
所得によりかなり違うので確認して下さい。
年末調整や確定申告で清算

実は、給与明細は確定事項ではありません。
ほぼ暫定の数字です。
サラリーマンの方は、年末調整や一部確定申告で今年の所得と税金が確定します。
自営の方は、確定申告で今年の所得と税金が確定します。
税金を抑えることは所得を上げることに直結します。
是非、見直しから進めて見て下さい。
ひょっとしたら思わぬ収穫があるかもしれません。
本記事を参考に、給与明細を元に現状を見直し、節税に役立てられれば幸いです。
時間がない人はここまで見直してから、副業のことを考えてみましょう。